第三話 反乱前夜(15)
さらに時は流れ、アンドレスがアパサの元に来て、はや半年が過ぎていた。
最近では、アパサは自らも棍棒を手に、アンドレスの相手をするようになっていた。
アパサの攻撃は常に、アンドレスにとって、単にその技術的な未熟さを突きつけるに留まらず、むしろ心理的に突き崩してくる種類のものだった。
アパサは、アンドレスに対して、己の攻めが利く部分は敢えて攻撃してこなかった。
そのかわりに、アンドレスが最も得意とする技や、最も強い部分、そして、アパサにとっては切り込みにくいであろう部分を、逆に狙って攻めてくるのだった。
アンドレスにしてみれば、常に自分の自信のあるところを攻め立てられ続けるため、逆に、心を攻め込まれた状態になってくる。
そのようなアンドレスの心の恐れや惑いをアパサは瞬時に読み、後は軽く裁いてあっさり勝利した。
アパサは冷ややかな眼差しで、アンドレスを見下ろした。
「単にやれと言われたことを言われた通りにやっているだけでは、強くなどなれないぞ。
常に、頭を使え。
技の問題だけではない。
敵の心を攻め切って、勝て」
アンドレスは、幾度となく聞かされてきたアパサの言葉に、苦々しい思いで「はい」と答える。
「これは単に戦場だけのことではない。
どのように強大に見える敵でも、常に隙が無いなどということは絶対に無い。
相手の心を読み、相手の嫌がることをしろ」
アンドレスはアパサを、改めて見上げた。
アパサの目は不遜ではあったが、ひどくまじめでもあった。
「敵を切るには、何が必要か。
それは、敵を崩すこと。
では、どうすれば崩れるのか?
常にそれを考えろ。
いいか。
これは、戦場だけのことではない」
そして、少し言葉を区切って、再び続けた。
「おまえもだが…、トゥパク・アマルも、俺から見れば、あまりに真っ向からクソまじめにいきすぎる。
時に、廉潔は命取りになる。
それだけではない。
味方さえ危険に晒しかねないのだ」
そして、アンドレスを改めて見据えて言う。
「アンドレス、おまえはもっとずるくなれ」
アンドレスは返事に詰まった。
が、何か、アパサは重要なことを言おうとしているのだ。
武器を手にしたまま、アパサは空を見上げた。
「そろそろ、また冬がくる。
トゥパク・アマルはいつ動くのか…」
アパサは独り言のように呟いた。
アンドレスも、つられるように空を見上げる。
乾いたこの土地の秋空は、まるで吸い込まれそうに高く、眩暈を誘うほどに澄んでいた。
そして、冬が訪れても、アンドレスの特訓は変わらず続いた。
むしろ、その内容はいっそう熾烈なものとなっていた。
この頃になると、アパサは自分の部下たちをも呼び寄せ、複数の人数での切り合いを行わせるようになっていた。
中央にアンドレスを立たせ、その周りに円陣のごとく、腕の立つ部下たちを6〜7名並ばせる。
そして、周囲の者がランダムに中央のアンドレスに向かって切り込むというものである。
すべての敵を倒すまで、アンドレスは戦い続けなければならなかった。
しかし、相手はアパサのもともとの訓練下にある精鋭たちであり、そのような相手に複数でかかってこられては、太刀打ちのしようもなかった。
闘っているうちに、次第にある種のトランス状態になってくる。
そこまでくると、時に不気味なほど技が冴えることもあるのだが、ある点を超えるとついには意識がプツッと途切れてしまう。
特訓中に幾度も意識を失いながらも、その過酷な円陣訓練は続けられた。
さすがに、この頃になるとアンドレスも精神的に打たれ強くなっていた。
もともと永きに渡り侵略者に理不尽に虐げられてきたインカに人々は、表に出す出さぬは別として、反骨精神が強かった。
さらに、アンドレス自身その素養として、その純粋さが故に、己の信念に反するものには真っ向から立ち向かう闘争的側面を多分に有していた。
それらが、アパサの指導によって、良くも悪くも刺激され、開花していった。
今や、どれほど敵に倒されようとも、立ち上がっていく底力をいやがおうにも体得しつつあった。
ところで、今でも、早朝の雑巾がけは変わらず続けられていた。
冬の水は指がちぎれるほどに冷たかったが、この頃になると、アンドレスはこの作業に単なる手首の筋力強化に留まらぬ意味を見出していた。
早朝のまだしんと静まり返った館で黙々と床を拭いているとき、不思議と彼の心は静かに澄んでいく。
余計な複雑なこと、雑念は、どこか遠くに消えていく。
頭も心も無になっていく瞬間だ。
彼にとって、今やこの早朝の日課は、意図せずとも「無心」を体得するための、願ってもない自己鍛錬の場でもあったのだ。
アンドレスは、そろそろ1年になるアパサの特訓を通して、自らの心の動かされやすさというものを嫌になるほど自覚していた。
元来の感受性の豊かさは、これまで生きてくる中で、表面に隠された物事の本質を見極めるために大いに役立ってきたものではあった。
しかしながら、それと共に、今やいかなる状況にあっても、常に己の心を平静且つ冷静に保つことのできることが必要でもあることを認識していた。
人に勝つ理をいかに学ぼうとも、まずは己に勝てなければならない。
そうした不動心を鍛えること…――アンドレスは身体的な技の向上と共に、そのことをこの後の訓練の眼目の一つと自ら定め、日々の訓練に臨んでいった。
さらに、アパサの指導は、武術的な特訓に留まらなかった。
もともとアパサは戦術に長けた武将でもあり、トゥパク・アマルがこの男にアンドレスを託した理由の一つはそこにもあった。
火器を持つことを一切禁じられているインカ側の反乱軍が、鉄砲、大砲などの火器を多量に投入して対抗してくるスペイン軍にいかにして立ち向かうのか。
実際、それは、トゥパク・アマルの頭を今も非常に悩ませていたことだった。
しかし、いかに智略に長けたアパサと言えども、それは容易に回答を出し得ぬ難問だった。
今、アパサにできることは、アンドレスが戦場で兵を率いる将となった暁に、澱みなく的確な判断と決断が行えるよう、アパサ自身の中に蓄積されてきた一般的な戦術を、最大限指南するのみだった。
後は、その場の実際の戦況を緻密に分析しながら、臨機応変に、且つ、精緻な策略を練り、対応していくしかないのだ。
毎晩、夕食後の時間、アパサはアンドレスを前に座らせて、戦術の指南を行った。

今宵も、アパサは蝋燭の灯りの下に地勢図を広げ、武術指導と変わらぬ厳しい面持ちでアンドレスの前に座っていた。
「平原における戦いでは、高地は常に戦略的要地となる。
高地は敵陣地を瞰制できる上に、守備陣地としても、攻勢にでる際の発起点としても、有利だからだ」
アンドレスは、頷いた。
アパサは、さらに続ける。
「だが、この国はアンデス山脈が連なり、高地や山が連綿としている。
こうした土地柄では、高地を占拠することが、逆に命取りになることもある。
なぜか、分かるか?」
アンドレスは再び頷いて、地勢図の中の一つの山脈の周りを指でなぞった。
「高地の周りにあるこの低地を敵に占領されてしまったら、高地に陣を張った部隊は包囲されてしまいます。
しかも、後方にも山々があり、かえってそれが障害物となって、退路を絶たれてしまいましょう」
「そうだ。
そうなると、どうなる?」
「味方の補給は絶たれ、降伏せざるを得ないと思います」
アパサは、冷ややかな声で問うた。
「そうなったら、おまえは敵に降伏するのか?」
アンドレスは蝋燭の向こうで、冷たい眼差しを向けている師の顔を見た。
「実戦は必ずしも理屈は通らぬことがある。
場合によっては、不利になることを承知で、この地形でも高地に布陣を敷かねばならぬ戦況も出てくるだろう」
アンドレスは息を詰めた。
「まあ、いい」と、冷たく言ってアパサは再び地勢図に視線を戻した。
「もし高地にいて周囲の低地を優勢な敵に占拠されるようであれば、機先を制して下山し、後方陣地に撤退する必要がある。
だが、それも、その土地の地形、敵の布陣にもよるのだ」
そう言いながら、アパサは地勢図を丸めて元の場所に戻した。
「山岳戦をやるには、柔軟防御を実施できるだけの指揮能力が必要だ。
つまりは、それだけ山岳戦は難しいということだ」
そして、訝しそうにアンドレスを見た。
その目は、「果たして、おまえにそれが指揮できるのか?」と、言わんばかりの色だった。
アパサは腕を組みながら、椅子に反り返った。
「仮に、逆にスペイン側が高地に陣を張り、我々インカ軍が低地を占拠したとしよう。
恐らく、敵も同じように機先を返して下山を試みるだろう。
だが、それと共に、奴らは背後の高地に砲兵隊を配置し、低地に結集したインカ軍を砲撃してくるだろう。
火器の威力は凄まじい。
恐らく、少数の砲兵隊に我々は蹴散らされ、たちまち戦況は奴らに有利になるかもしれん」
そして、アパサは考え込むように押し黙ってしまった。
蝋の残りが少なくなった蝋燭の炎はひどく不安定に揺れながら、険しい表情で宙を見つめるアパサの横顔に深い影を落としている。
アンドレスとて、火器がない状態でいかに戦って勝利に導くのか、そのことを考えない日はなかった。
彼は、いっそう揺れの激しくなった蝋燭の炎を見つめた。
「銃を手に入れればよいのではないですか」
不意に沈黙を破ったのは、アンドレスの方だった。
「銃そのものは、この国にあるのです。
スペイン人が持っているだけであって、それをうまく手に入れればよいのではないですか」
アンドレスは、思っていたままを、思い切って話した。
「方法を考えればいいのです。
手に入れるための方法を」
アパサに何を言われても構わない。
アンドレスの眼差しには、覚悟の色が見える。
だが、意外にもアパサの罵声は飛んではこなかった。
「それはその通りだな。
だが、実際には、かなり難しいだろうよ。
それに、たとえ手に入っても、そう大量には無理だろう。
だが、確かに、手に入れる方法を考える価値はある」
アパサは、いつものようにチチャ酒の樽の方に酒をつぎに立った。
そして、二人分の酒をついできて、アンドレスの前に差し出した。
「おまえも、たまには飲め」
アンドレスは、軽く礼を払って、波々と酒がつがれたカップを受け取った。
チチャ酒とは、古来からアンデス地帯で愛飲されている、伝統的なトウモロコシを原料とする酒である。
アパサはチチャ酒を一気に飲み干して、さっさと二杯目をつぎに立つ。
アンドレスもカップを傾けて、まだあまり飲みつけぬ酒を喉に注ぎこんだ。
口いっぱいに、酸味のある葡萄のような味が広がっていく。
「いずれにしても、火器がない状態でいかに戦うかを考えておく方が先決だ」
二杯目をあおりながら、アパサは話の続きをはじめた。
「地勢や気象条件をうまく使うこと。
これは、当然のようだが、意外と侮れん。
それから、接近戦に持ち込むとうい方法もある。
他は?
おまえなら、どうする?」
再び、アパサが問う。
火器が無い状態で、火器を大量に保持する敵といかに戦うのか…――そのアパサの問いに、アンドレスは、やはり普段から考えていたことをそのまま答えた。
「奇襲です」
「奇襲?」
アパサが、色の見えない声で応じる。
「はい」
能面のような表情でアパサはアンドレスの目を覗く。
しかし、すぐに、にんまりと、アンドレスには意味を解(げ)しかねる笑みを浮かべた。
「おまえは真正面から行くタイプだと思っていたがね」
「ずるくなれと言ったのは、アパサ殿ではないですか」
思わず、アパサは苦笑した。
が、すぐに冷ややかな眼差しに戻った。
ふいに蝋の無くなった蝋燭が消え、真っ暗闇に包まれる。
蝋の臭いが部屋の中に立ち込めた。
「残念ながら、奇襲も、そう簡単ではないな。
恐らく、火器を手に入れるよりも難しいかもしれん」
アパサが闇の中で話すのを聞きながら、アンドレスは席を立った。
そして、既に我が家のように把握しているその部屋の棚の一角から、真新しい蝋燭を取り出し、火をつけた。
再び、部屋の中が蝋燭の炎で照らし出される。
「戦場で最も敵が弱点とするポイントを見抜いて奇襲をかけるには、天才的戦術を必要とするものなのだ。
そして、かなりの強運もなければ駄目だ。
わかっているのか、おまえは」
アパサは、溜息とも取れる息を吐いた。
「奇襲を成功に導ける天才的な戦術家など、実際、何百年に一人出るか出ないかだ。
残念ながら、トゥパク・アマルも、俺が見る限り、そこまでの戦術的天才ではない」
その声には嫌味な感じが全くなく、非常に冷静であっただけに、アンドレスの中にいっそう不穏な気持ちを掻き立てた。
「トゥパク・アマル様では、駄目だと?」
冷静を装うアンドレスの声が、しかし、微かに揺れている。
「トゥパク・アマルが駄目というのではない。
ただ、奇襲を成功させられるほどの天才は、極めて稀だと言っているのだ。
だが…」
それから、酒を置いてアパサは真正面からアンドレスに向き直った。
アンドレスも、つられるように姿勢を正す。
「武器で著しく劣るインカ軍が勝つためには、奇襲が必要な時がくるだろう。
残念ながら、我々は天才ではないかもしれん。
しかし、的確な情報収集と正確な分析、時機の把握と正確で果断な行動、押さえるべき要点を押さえさえすれば、少なくとも奇襲の成功率を高めることはできる」
アパサのまるで未来を予見するかのごとく厳しくも真剣な眼差しに、アンドレスはその教えを深く我が身に落とし込むように、力強く頷いた。
やがて、アンドレスがこの地を訪れて2度目の春が過ぎた。
この時、既にアンドレスは17歳。
アパサの厳しい鍛錬のもと、彼は見違えるように逞しい若者に成長していた。
そして、その年の夏も過ぎる頃、アパサの指導はそれまでとはやや趣を変えたものとなっていた。
実際、ここにきてアンドレスの成長は目覚しかった。
1年半に及ぶ過酷なトレーニングの継続により基礎的な身体能力は高められ、アパサが徹底的に基本を叩き込んだ成果も実を結び、今や彼は棍棒をまるでサーベルのごとく軽々と自在に裁きながら、複数の相手を同時に圧倒するまでになっていた。
アパサが心理戦に持ち込もうとも、アンドレスはそれほど動揺することも、もはや無い。
円陣訓練で、アパサの部下たちをまとめて片付け、丁寧に汗の処理をしながら呼吸を整えているアンドレスの傍に行くと、アパサはおもむろに言った。
「これからは、美しく、ということを念頭に置いてやってみろ」
アンドレスは一瞬、耳を疑った。
どちらかと言えば、いかに泥臭く、血生臭くとも、何が何でも敵を倒す、ということを叩き込まれてきたのだ。
ましてや、「美しい」という単語がアパサの口から出たことに、まずアンドレスは驚いたし、決して嫌味な意味ではなく、意外でもあった。
「美しく、ですか?」
余計な質問をすることで、これまで幾度と無くアパサの罵声を浴びてきたアンドレスだが、この時は思わず口をついて、そんな言葉が出てきてしまった。
アパサは、まじめな顔のまま「そうだ。美しく、戦え」と繰り返した。
「おまえは、ただ敵を倒せればいいのではない。
美しく倒さねばならい。
あのギリギリの泥沼の戦場の真っ只中でもだ。
何故なら、おまえは、偶像にならねばならぬからだ」
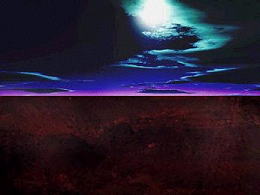
二人の間を、砂の混じった一陣の風が吹き抜けていく。
そろそろ夏の終わりも近い。
既に冷気を帯びた風が、再びこの乾いた高地を吹き渡る季節になっていた。
アンドレスは汗を拭く手を止めたまま、アパサの言葉の意味を何とか咀嚼しようとした。
しかし、その意味がよく分からない。
アパサは、「おまえの察しの悪さは相変わらずだな」と嘯(うそぶく)くと、改めて真正面からアンドレスを見据えた。
「おまえの戦場での振る舞いの一つ一つが、いや、戦場だけでなく、人前に立ついかなる場面でも、インカ皇帝の血統として相応しくなければならぬのだ」
アンドレスは、ハッとした瞳でアパサの顔を改めて見た。
アパサの目は、めったにないほど澄んでおり、どこか、まるで同情の念を宿しているかのような色さえ湛えている。
「それが、おまえの宿命だ。
アンドレス。
おまえは、周りの者の心を惹き付け、奮い立たせ、士気を高める、そのための偶像にならねばならぬのだ」
そして、低い声で続けた。
「今、トゥパク・アマルがやっているようにな」
アンドレスは、今や、はっきりとその意味を察した。
そして、トゥパク・アマルがわざわざ自分をこのアパサの元にあずけた理由も、今、アパサの言葉で明確に認識した。
確かに、銃や砲弾で応戦してくるスペイン兵に対して、アンドレスがいかに見事な剣裁きで立ち向かおうとも、そこには、さほどの大きな意味はない。
むしろ、反乱軍の精神的支柱としての「インカ皇帝」つまりは「トゥパク・アマル」の属性の一部として、インカ族の人々の士気を高め、その魂を高揚させることにこそ意味があるのだ。
それ故、「インカ皇帝」の側近、あるいは血統の武将として、いかに味方の心を打つ振る舞いができるのか、その見せ方が重要だと、アパサは言いたいのだろう。
既に、辺りは澄んだ藍色に染まりはじめている。
秋近い夕暮れ時の空気は、何とも物悲しい。
足元のすぐ傍の草の中から、虫の鳴く声が響いてくる。
アンドレスは、すっかり手になじんだ棍棒の感触を改めて確かめた。
「わかりました」
「うむ」と短く答え、アパサは館の方に消えていった。
一人草地に立ったまま、アンドレスは宵の空を見上げた。
ただでさえ乾いたこの土地の秋間近の空は、恐ろしいほどに澄んでいる。
まだ微かに薄明るい空には、しかし、星々が既に秋の星座を描きながら、白く清らかに瞬きはじめていた。
無性に故郷が懐かしく思えてくる。
星の静かな瞬きが、今は、何故かとても切なく感じられる。
すっかり夜の帳がおりても、アンドレスはじっと遠い星を見上げたまま、いつまでも冷たい風に吹かれていた。
その日を境に、これまでの特訓に加えて、いかに美しく見せるか、という研究がはじまった。
果たして、美しく見えるとは、いかなることなのか。
アンドレスは、人間の動きよりも、むしろ、自然界の野にいる動物たち、そして、空を舞う鳥たちの姿に、美しさの要素を見出していた。
一縷の無駄もない動き。
動物たちの、どのような他愛のない動きさえ、美しい。
それは、とても合理的な動きとも感じられた。
人の目、いや、脳というものは、合理的な動作を見ると美しいと感じるのではないか。
故に、基本を叩き込まれたアンドレスの動きは、その素養を既にもっている。
基本こそが奥義…――かつて、まだ訓練初期の頃のアパサの言葉が、アンドレスの中に甦る。
その境地を、今、己の中に結実させようとしているのだ。
実際、アパサのこれまでの特訓は、無駄の無い、まさしく合理的な動きをひたすら追求してきたものだった。
合理的な動きであることは換言すれば、「理にかなっている」ということであり、理にかなっていれば、それは自ずと「強い」、つまりは「利がある」動きということにもなるのだ。
美しさには「理」と「利」がある…――。
そこを追求することで必然的に華のある美しい動きも生まれるに相違ない。
それは、単なる表面的な動作に留まらず、当然ながら精神的な側面をも含むものである。
こうして、強さと共に、美を追求する特訓が新たにはじまったのだった。



